
abstract and subject

flora
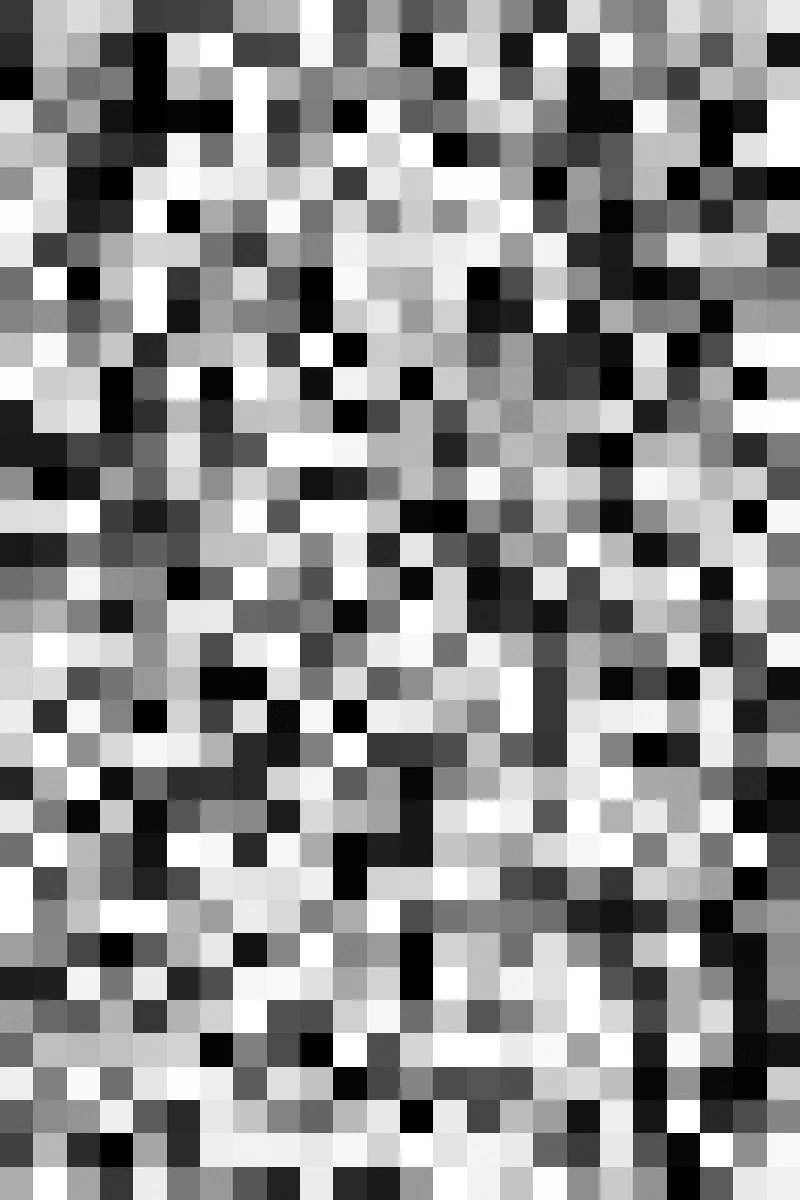
kyoto
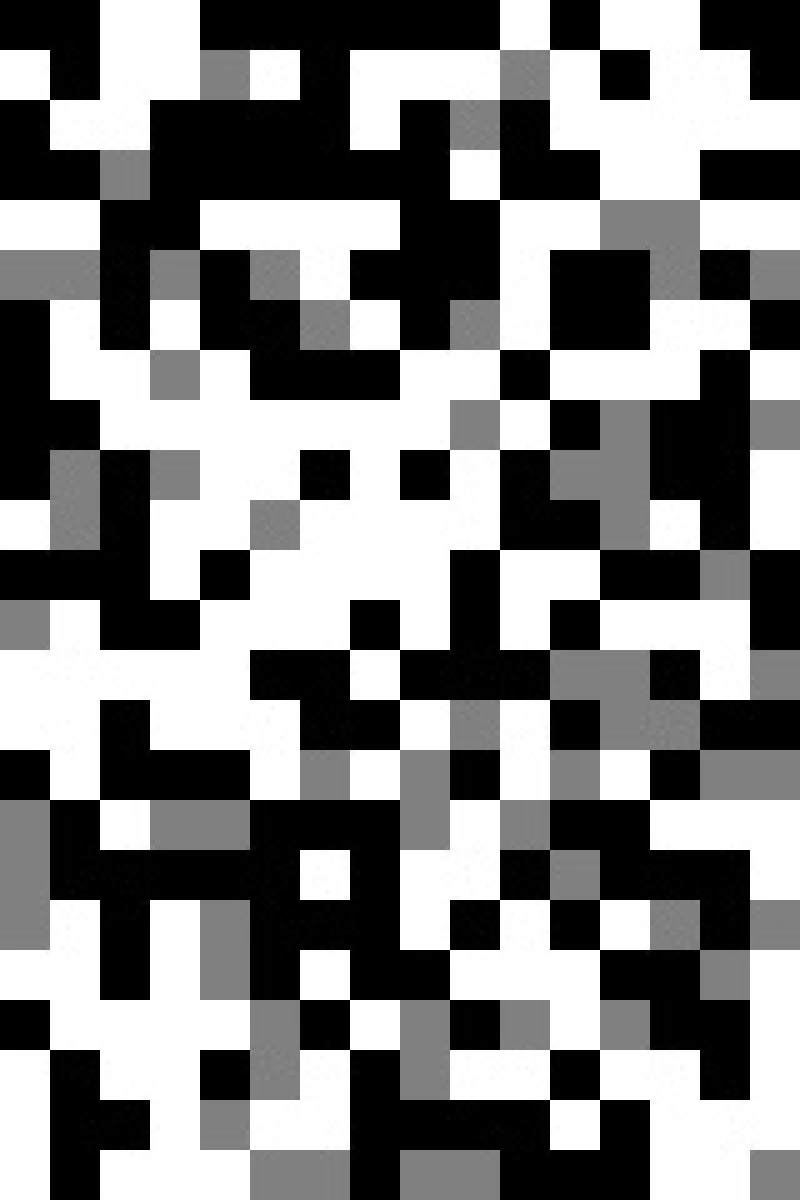
pikachu
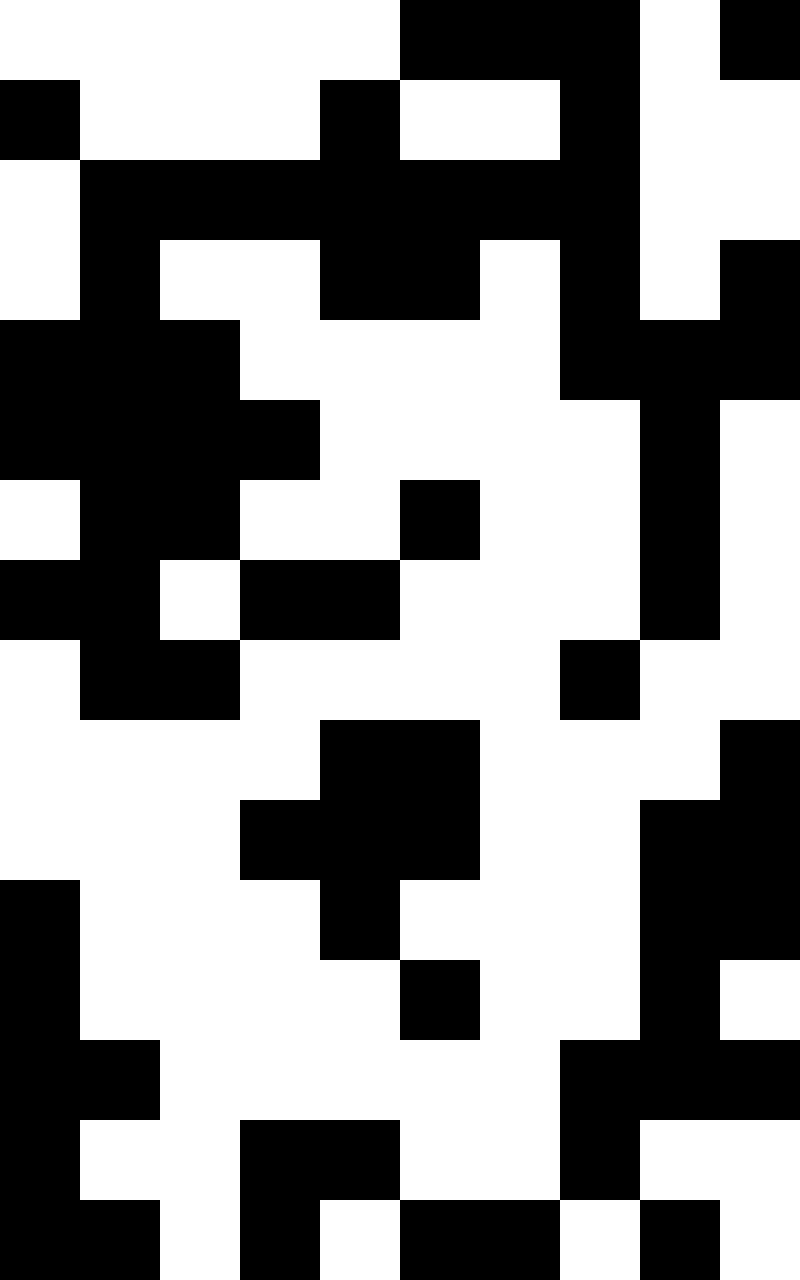
mirror

freedom

cat

miura



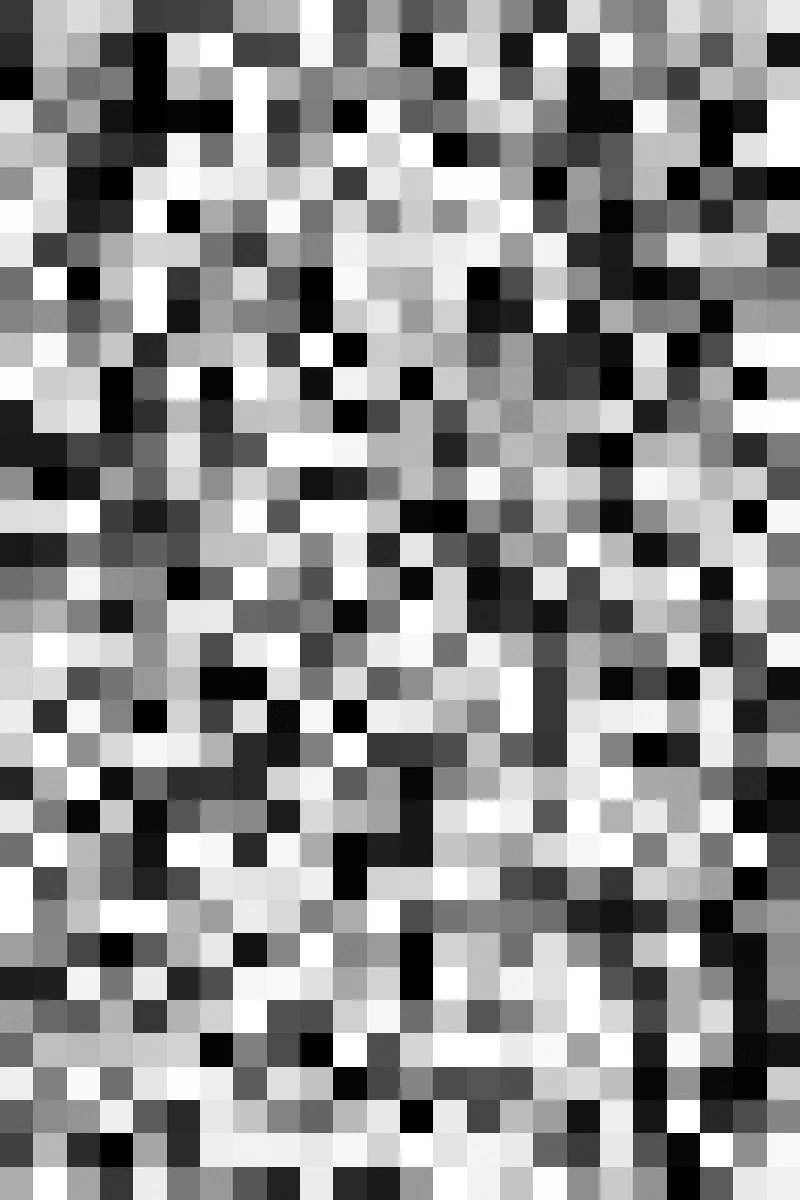
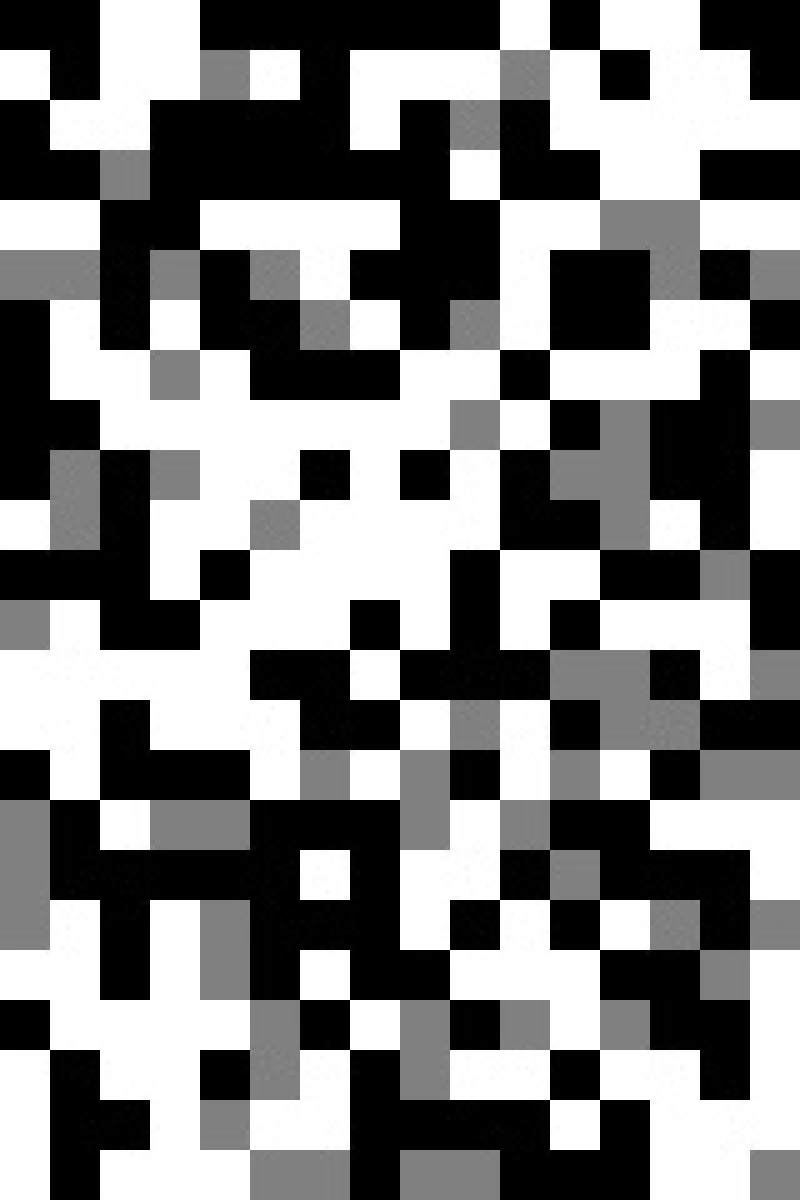
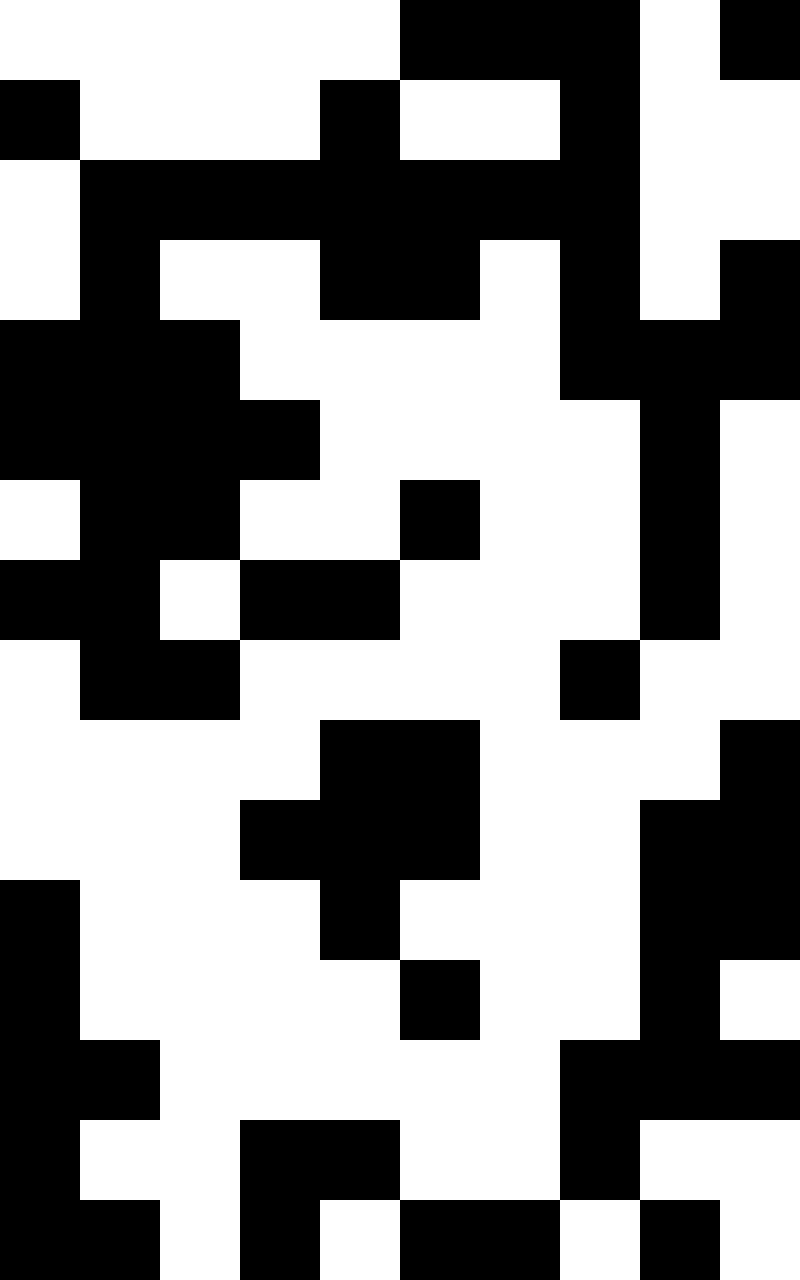




写真的な、余りに写真的な。
これはあるキュレーターの方から頂きました私の制作への批判について、私のその時点での所存を明確にしようと書いた文章であるために、語気が強くなっていたり、芸術性のないものとなっていることをお許しください。
これまで写真や映像は、人間の知覚の範疇で、時間や空間、身体との密接な関わりのなかで手懐けられてきた。こうした利用に奉仕する写真や映像の集合には、共通してある文法が立ち上がり、こうしたものを私たちは写真や映像の文法だと思って扱ってきた。しかしこれらの文法は視覚や聴覚を含む人間の知覚、そして身体の有する構造の虚像として生じるものであり、『写真』や『映像』というものの有する構造に基づいていたり、もっとひどければ関連したものですらない。つまり私たちがこれまで映像文法あるいは映画の文法だと思ってきたものは、映像や写真においてなんら本質的なものではなく、実際には人間の知覚において本質的なものなのだ。私は、写真や映像の置かれたこうした状況に憤りを覚える。そして、こうした状況から写真や映像を自由にし視覚を失った写真——いや余りに写真的で、視覚以前の写真を考えてゆきたい。そのとき重要なのは、感光した空間中の平面における形質であり、その意味で私たちが扱うのは、写真的な空間中の平面である。
私たちに奉仕しない『視覚を失った』映像や写真の本性的な在り方において(映画の黎明期にはかえってこうしたことは明らかだったように思うが)例えばある写真と被写体やある映像と音声とはいかなる絶対的な関係を持たず、また写真・映像といったものは私たちの視覚とも関係していない。この場合、ある音楽を伴ったパフォーマンスを撮影したフッテージを編集する場合に、そこにある音楽を主体にすることや、あるいはパフォーマンスを主体にすること、またそれらを調和させることのいずれも映像の本性においては何ら排他性をもって有意義なことではない。より厳密には、映像や写真は、任意の運動が時空において示す事象を、例えば視覚的な認識の範疇で調和させるといった些末なことを目的としない。むしろ、写真や映像は視覚的な認識において時間や空間の構造や調和を失わせ、統合を失調させ、被写体の全てを殺すために動員されていると知覚され理解されるような場合に、人間の知覚から解放され、自由な状態を回復していると言えるだろう。
映像や写真が人間の知覚にその可能性を閉じ込められてきたこのような状況は、占星術やある時期までの天文学と類似していると言えるだろう。つまり、人間が星々について、自らの理解の範疇で意味を見出そうとする仕方が、今日私たちの多くが映像や写真をみるときの方法に似ているということだ。占星術において、人類は星々の位置やその変化といった現象の一部を観測し、その意味を『自らの世界』にある語彙において見出した。そのとき人間は知覚すること、そして観測することが可能なさまざまな刺激や事象のなかから人間にとって目立ち、重要だと思えるような取り掛かりを見つけ、座標化したり、名前をつけたり、指標化するなどし、さらにはそれらを自らが経験的に有する語彙や概念、事項と対応させることで自らに引き寄せ、意味付けした。しかしこれらの理解の総体に立ち上がるのは、今日の映像の受容と同様に、もっぱら人間の知覚やあるいは文化や社会の有する構造の虚像であり、それは『星々』それ自体が有する構造や全体性に基づいていたり、もっとひどければほとんど関連したものですらないということは明らかだろう。つまり、映像や写真、音響といったメディウムは天体と同様に、それが光学的であったり化学的であったり物理学的であったりする自然の現象であるために、人間の知覚やある時点での人間の英知に意味や全体性の限界を持たない。つまり、絵画と異なり、ここで議論の中心にあるようなメディウムは人類の知覚や経験にとって星々が有するのと同様の理解不可能性を本性的に有するのだ。
無論、これまでそうであったように、知覚や経験における理解不可能性を本性的に有するメディウムを人間の知覚や経験の範疇で扱うために、その全体性を意図的に見落とし翻訳することは可能だ。例えば写真においても、人間がイメージをつくりだすに至る欲望に注目するなどし、その他の部分を意図的に見落とすことが試みられてきたし、実際、これは所与の写真を『理解』するためには有効な手段である。なぜなら、これまでに活動した作家たちも含めた一般的な人間が写真的イメージをつくりだすに至る欲望は通常、現実のイメージや経験から発生し、したがって現実のイメージや経験と直接に関わっているものだからだ。ただし重要なのはこうした手法が、あるものを社会や文化、時間や空間の認識といった私たちの身体性や知覚に依存した観測や理解という範疇において理解するために便利な処理に他ならないというまさにこの事実であり、これが占星術や天文学の初期に星々を理解するために人間が用いた方法と似ているということだ。
こうした理解の仕方はある人間が未収得のある言語をすでに収得した言語との対応関係において——つまり例えば常に翻訳しながら理解しようとする態度にも類似している。この類比で重要なのは、その言語のなかで生きることが、ある言語の全体性や意味を汲み理解するために重要だということである。また翻訳や占星術との類似は、なぜ私たちが映像や写真を手懐けようとするかについても教えてくれる。つまり写真や映像の魔術性の中に取り込まれることに畏れを抱く私たちがその魔術性を抑圧し、それらを手懐けることで自らのこころのやすらかさを保とうとする、私たちの余りに人間的な反応が、写真や映像というメディウムの扱い方において現れているのだ。私たちの視覚や聴覚、時空の認識から逸脱しているものへの畏怖の感情そのものには、私たちの過去の多くのことを――占星術や初期の天文学、差別や迫害といったものを——重ねることができる。しかしながら、やはりこのような状況に、ある時点で持ちうる全てを用いて挑戦するか、あるいは問題の一部を意図的に見逃し矮小化することで無力化を図るかという二つの態度は酷く隔たりのあるものだ。ただし先にも述べたように今日映像や写真と向き合う作家たちも、もっぱら社会や文化や視覚、意識やこれらに類する事項に自らの興味や関心を矮小化させている。よって、既出の一般的な作家の作品を分析するということに目的を絞る限り、占星術的な分析や理解は有効である。あるいは、この場合、今日行われている分析や理解を占星術的だと言って批判することはできない。しかし、映像や写真の本性に対して余りに人間的であって、不誠実なまでに極端な一部においてすべてのことがなされていることに変わりはない。
絵画においては絵具や絵筆といった媒介物が人間に寄り添うように抽象化されている一方、彫刻において物質は一定程度以上のアクチュアルさを有していると言えるだろう。アクチュアルな物質や素材というものと、同様にアクチュアルな存在である人間が格闘し、そのなかである彫刻が立ち上がってくるようなことがあるとすれば、対して写真は、その本性的な在り方——つまりその概念や定義の中心に近い部分において、人とは上記の二つのメディウムと異なる関わり方をする。つまり、写真や映像においては人間が抽象化され、写真にとってアクチュアルなものになるとき、こうしたメディウムの自然な状態が訪れるのだ。私はずっとまえから、写真的で、余りに写真的な写真を欲し、視覚以前のものを感じていたが、写真と関わるときに感じていたこの違和感や直感は、まさにこの本性によるものなのだろう。つまり私たち人間が絵画における絵の具や絵筆やキャンバスのように抽象化され、理想化され、客観的なものである時に、写真や映像が自然な状況にあるというこの関係性への直感と、しかしながらこの関係性から大きく逸脱した写真作品や映像作品のみが、今まで人間によって作り出されてきたことに対する違和感がずっとあったのだろう。
写真の出口にたむろする人間を排除し、写真から視覚を失わせることは、今まで試みられたことのきわめて少ない写真の可能性の全世界のなかの未開の地であり、この危険で魔術的な世界に飛び込み、視覚を失った写真について考え、写真の可能性を汲み尽くすことは、現代以降の写真作家における喫緊の課題である。写真をみる者が、未だこのような意識を持たないことには正当な理由を認めるが、しかし扱う者が未だそうでないことにはなんら正当性がない。自らの心の安らかさのために写真や映像という崇高なメディウムの本性を無視して手懐けるのではなく、その本性や全体性のなかで生きようとする者は、それぞれのメディウムにおいて汲み尽くされるべき重要な可能性が隠れる——最大限の敬意とともに、あえて次のように言う——野蛮で未開な地で、人知の先で、そして視覚以前で、新たに生きなければならず、そのために私たちは抽象化され、写真のアクチュアルさに寄り添わなければならないのだ。(2023/5/29)
さようなら、そして、はじめまして写真。
祖母が旅行先で撮った写真を見ることが写真と私との出会いでした。私の祖母は写真を撮る人で、異国の建築や人々、日本の山々や海岸、地層を写真におさめていました。そして、ときどき祖母に会う時には、彼女の撮った写真を彼女の説明とともに見るわけですが、私は彼女が写真を通して、そうしたもの(人々や建築、風景など)と関わろうとするのを小さい頃からずっと、断続的に見てきました。つい先ほどそう述べたようにこれが私にとっての写真との出会いではあったのですが、同時にこれはずっと不思議でした。そして、自分で写真を撮るようになっても、この疑問はより深まるばかりでした。
祖母の写真の中にはとてつもなく美しいものもありました。しかし彼女はその美しさには目もくれず、写真を通り越した先にある被写体や旅行の物語そして社会問題、またはその手前にある自分の感情や体験、意見についてしか話しませんでした。私は写真を通して、あるいは写真をきっかけに何か他のものを見たり知ったり関わったりしようとすることにずっと強い違和感があって、やはり写真と触れたおおよそ初めての頃から、写真にとって外側にあるものでしかない『世界』との関係にはどうしても手が届かなかったのです。ある写真の中に私や写真にとって正直なものがあるとすれば、それは写真と私との関係のうちにのみ存在するもので、その他のものは私や写真にとって不誠実なものだと、私はただ直感的にそう思うのです。
✳︎
私は手動でピントを合わせるマニュアルフォーカスレンズを使って写真を撮ることが大好きです。またカメラもマニュアルモードに設定して、シャッタースピードや絞り、そして感度なども全て手動で合わせて写真を撮影しています。少し込み入った話になってしまいますが、マニュアルフォーカスレンズでピントを操作するためには、レンズについている『フォーカスリング』という部分を回してレンズを操作します。また古いレンズだと、絞りを操作するためにも、レンズについた絞り環という部分を回さなければならないのですが、私がフォーカスリングや絞り環を回すその物理的な力がまさに絞りやレンズの位置や状態に繋がっていて、そのことによって私は情報をレンズとシームレスにやり取りすることができるのです。このとき私にとって、フォーカスリングの回転や絞り羽根の状態の変化とそうした変化によってじんわりと変化してゆく像が最も、そして他の何よりも大事なこととなってしまいます。そして、この体験がずっと私にとっての写真であって、私が写真において最も愛する体験なのです。言葉を返せば、このとき被写体や光景、私の社会的状況や感情、感覚、あるいは光景や被写体に対する私の感情も含めた写真の外にある他のすべてのことが、ほんとうに、ほんとうに——ほんとうに、どうでもよくなってしまう。この体験が私にとって重要な写真的なものなのです。
このようなことが、撮影時にはレンズのピント距離や絞りの他にもシャッタースピードやフィルム、現像時にはフィルムの銀塩やデジタルのピクセル一つ一つにおいて成り立っているように感じます。だから、街で写真を撮っていても、像に関する興味はとても強いものの、周囲の状況にはむしろどんどん本質的な関心を失ってゆくようで、心ここに在らずという感じになってしまうのです。このように写真を撮っている最中、カメラや、私が今まさに触れているレンズのさらに先にある光景や被写体が、今私が触れているレンズやカメラというものにくらべて大事なわけがないという感じが強まると、街中でもたまに泣きたくなるときがあります。カメラは私と同じように、実のところこの世界と何の関わりも持たず、孤独で、しかし彼は幸福な孤独と強さを持っているのです。
✳︎
フォーカスリングを回してゆくと、徐々にピントの合う位置や作り出す像の質が移り変わってゆくのがわかります(2024年の展示では会場に私の中判カメラを置いておく予定です)。指の動きがレンズを連続的に動かし、それは光速で変化する像ともつながっています。私はここに、唯一、私がこの深さで関われるものが存在しているのだと感じます。そのようなときに、どうしてみんな、光景や被写体に注目して、ときにはそのうえで感動などできるのか。私にはずっと疑問であり、なぜなら私は写真機が本当に好きで、私が写真を撮りたいと思うのは、ただ、カメラと私が密接に情報をやり取りし、新しい画像を生み出すことやその瞬間に得られるものを得たいと思うからなのだから。
ヴィレム・フルッサーという哲学者は『写真の哲学のために』という書籍のなかで「結局、写真家が作り出そうとしているのは、以前にはけっして存在しなかったようなさまざまな事態です。しかし、彼はそのような事態をその外にある世界のなかに求めるのではありません。なぜなら、彼にとって世界は作り出されるべき事態のための口実にすぎないからです」と述べています。この部分は、まさに写真機と私の関係を的確に言い表していると思います。私にとって被写体や光景は口実にしか過ぎません。人がなにか言い訳をするとき、口実は不可欠であり非常に重要なものですが、しかし言い訳の本質とはなんの関係もありません。同じように、もし写真においても、なにか一つでも感動のできる部分があるとすれば、それは口実の部分にではなく、ある写真が提示する装置の可能性の新しさや装置と機能従事者との関係性の中にあるはずなのです。
これはよく、ジェンダー写真論などで指摘されることですが、ある時期まで(そして今もかもしれませんが)女性や、あるいはある人が写真において『見られる対象』としてあったことの哀しさと同様の哀しさが写真にはあるのかもしれないと思います。つまり、多くの人が、写真を通して何か別のものを見ているということが、私にはそうしたことに似た哀しみを共有するように感じられるのです。そして、私なんかは、いままで私たちが写真をそうした方法で扱ってきたからこそ、ジェンダー写真論が問題とするような問題が写真において多発してきたのではないかと、強く思っています。つまり、そもそも、私たちと写真というものの関係性自体がそういった問題を内包しているのではないかということです。世界と写真と写真家、あるいは被写体と写真と写真家における屈折した関係を前提として私たちは写真の受容や製造——歴史を推し進めてきた過去があり、それが写真と私たちの関係において本質的な問題だと思うのです。そして私はこのような写真との関係に別れを告げようと思っています。
さようなら、そして、はじめまして写真。
さようなら、すべての人間とその視覚のための写真。そしてはじめまして写真——あなたとの対等で誠実な関係を願って。(2023/7/2)
世界と写真と写真家
写真において絶対的に重要で問題となることは、写真と世界がどのような関係を結んでいるかということや、また、写真と写真家がどのような関係を結んでいるかということ、そして写真家と世界の関係というものなのだと思います。これは、写真という定義が示しうる最も広い範囲においても重要であるような問題であると思います。つまりこれは、写真がある『構造である』とのみ定義した場合に重要であることです。また、もう少し限定的にはなりますが、しかしほぼ全てのいわゆる写真についてあてはまる問題としては、平面性や平面における形質という問題があるように思います。これは写真が構造であるということに加えて、写真が平面における広がりであり、私たちの視覚的世界においては、それが視覚される対象として存在するのだと仮定した場合のことですが、この定義は私たちが写真といって思い浮かべることのできるもののすべてを内包していると言って差し支えないと思います。何れにしても、私がここで言いたいのは、私はこうした写真の持つ本性的な性質を把握して、そのなかで写真的行為を行いたいと思っていることなのです。
私は『事物に抽象的な写真』という言葉を2020年ごろから、そして『写真的空間平面』や『感光した空間中の平面』そしてそれらにおける『形質』という言葉を2022年ごろから作品のタイトルなどに使い始めています。『事物に抽象的な写真』という言葉は、まさに先ほどの最も広い定義において重要になるような問題のうち、世界と写真との関係について言及しているものです。つまり、事物において——というのは被写体や世界と言い換えることができます——写真が抽象的な振る舞いをしているということを言っているのです。ここで重要になることの一つは、私はこの写真が『抽象写真』だと主張しているのではないことです。もっとも、写真の状態というのは常に一定であるのです。とまで言ってしまうと少し言い過ぎかもしれませんが、少なくとも感光平面というのは、感光する前も感光した後も一定の情報価値というのを持っていて、それは感光する前には潜在的な情報価値であり、感光した後は状態によって定義される情報価値を持っているということになるのです。そして、例えば全面を均一に白飛びさせてしまったり、現像の段階で真っ黒にしてしまったりなどして、その情報価値を棄損するという行為をすることは可能なのですが、しかし、その時には情報価値が写真的構造の外に向かって発せられることになるのであって、つまり写真が持っている情報価値は明確に棄損されない限り減らないのです。したがって、そこには『写真』か『棄損された写真』かしか存在せず、強いて言えば後者は『抽象写真』になるのかもしれませんが、それは写真という構造や存在においても抽象的な物体であって、ということは、もはやそれは抽象写真なのではなく、『写真において抽象的な物体』なのだと思うのです。ということで、私たちは単純な『抽象写真』などというものを得ることはできません。
しかしではなぜ私は『事物に抽象的な写真』などと発言することができるのでしょうか。それを説明するためにここで『事物において写真が抽象的な振る舞いをしているということを言っているから』という先ほどの説明に立ち戻ることになります。ある写真が事物において抽象的な振る舞いをしている時、その写真はなにも、それ自体の存在において抽象的になる必要はないのです。むしろ写真は非常にアクチュアルな存在の仕方をしていても構わないわけです。いや、むしろ写真というものがある種の強さやアクチュアルさを持って現前している方が、それは自ずと事物に寄り添いにくいものとなるので、むしろ事物において抽象的になりやすいとまで言えるかもしれません。そうした意味で、私は事物というものとの関係を曖昧にしてゆく作業を2020年ごろから続けてきました。そのなかで、初めは暈けや滲みを扱ってその曖昧さを強調するような、ある種、短絡的な作業に終始していたりもしたのですが、これは写真平面における『棄損』に他なりません。なので、次第に私は、写真は写真で被写体と並行して強い調和というものを目指せば良いのだと思うようになった時期もありました。またそうした時期を踏まえて、2022年ごろからは『写真的空間平面』という言葉を使うようになります。
『写真的空間平面』という言葉や『写真的空間平面における形質』という言葉は写真が持っている写真におけるアクチュアルさというものと密接に関係しています。以前にも引用しておりますがヴィレム・フルッサーという哲学者は『写真の哲学のために』という書籍のなかで「結局、写真家が作り出そうとしているのは、以前にはけっして存在しなかったようなさまざまな事態です。しかし、彼はそのような事態をその外にある世界のなかに求めるのではありません。なぜなら、彼にとって世界は作り出されるべき事態のための口実にすぎないからです。彼は装置のプログラムに含まれているさまざまな可能性のなかに事態を求めます。そういう意味では実存論と観念論という伝統的な区別は、写真によって乗り越えられます。つまり、現実的なものとは、外にある世界ではなく、装置のプログラムの中にある概念でもなく、まずは写真です。世界と装置のプログラムは、画像にとって前提に過ぎません。世界と装置のプログラムは、現実化されるべき可能性なのです。ここで、意味のベクトルの転倒が問題になります」などと述べています。ここで《写真的空間平面における形質》という2022年の夏に製作した5枚1組の連作を見ていただきたいと思います。この段階までに私は様々な感光平面や写真機と向き合うなかで、それらに共通する感光前と感光後の情報量・情報価値という問題を獲得していました。その上で、すべての写真の外側にあるものは全て写真にどういった形質をもたらすかという点においてのみ平等に重要であり、平等に瑣末であると考えてこの作品に取り組んでいました。つまり被写体といったようなものも、それが写真にもたらす形質においては重要であるが、その被写体が通常の視覚的世界においてどんな意味を持っているか、あるいは何であるかはといったことは重要ではないということを言っているのです。
またこのとき使っていた『写真的空間平面』という言葉は実は一種の短縮系で、本当は『写真的な構造のなかで感光し現像されプリントされた、空間中にある視覚可能な平面』といった意味を内包しています。これでは作品のタイトルなどで使用するのに長すぎるので、私は時間をかけて7文字にまでこの概念を短縮して表現しうる文字列を探し、この表現に至っているということです。ここでこれまでに述べたことの他にもう一つ重要なのが、実は短縮されてしまっている『視覚可能な』という部分であると思うのです。この部分は、写真というのは空間中にある視覚可能な物体であるということへの意識を強く持つことの重要性を示しています。また、この自覚の延長線上には、写真というのは、本性的には『見られる前のもの』であるという発見がありました。
よく写真というものは作家のビジョンの写しであるというようなことが言われます。こうしたことはシャーカフスキーに顕著だと思いますが、近年の写真作家や評論、またもっとポップな文脈ではインスタグラムなどのハッシュタグにおいても氾濫しているものです。少し話が逸れてしまうかもしれませんが、例えば『ファインダー越しの私の世界』『この世界はイロドリで満ちている』『写真で伝えたい私の世界』といったハッシュタグがありますが、こうしたものはすべて写真というものを透明な窓として扱っている上に、例えば撮影者が抱いたビジョンというものの写しとしての写真を規定しているものであるように思います。そのような意味で、こうした写真は基本的に『既に見られたもの』なのです。
しかし、こうした美学を持って写真を撮影している写真家の中にも、実際には少し先を行く者もいるような気がします。つまり、鑑賞者というものが写真家が抱いた感情やビジョンを共有するためには、既に見られたビジョンの写しを見てしまってはいけないということに気がつき、実際にはそのビジョンが生じるほんの一瞬まえの段階を——あるいはその伝えたいビジョンとは少しずれたビジョンをあえて写真として固定化し、視覚される物として現前させることによって、その写真が鑑賞された時に、目的のビジョンが鑑賞者の中で生じるように写真を制作する者もいるように感じるのです。これはラオコーンの議論とも似ているかもしれません。いずれにしても、実際のところ、写真がある写真家のビジョンの写しだということにした場合も、それを突き詰めると写真というのは実のところ見られる対象なのだということに立ち返ってくるのです。これが私の言いたいことでもあります。つまり、こうした美学からも、写真というものそれ自体は『見られる前』の『視覚以前』のものであり『視覚の対象』であるということが見出されるということは、非常に重要なことだと思うのです。
そういうわけで、私の最近の制作でよく用いる『視覚以前』という言葉は重要性を帯びてきたのです。そして、こうした視覚以前の物としての写真のあり方が、写真が写真的である場合であって、写真が自由でアクチュアルなあり方を示せるフィールドなのではないかと思っています。なので、私は写真の状態において非常にストレートで愚直で具体的なものを作りたいと思っています。しかしそれは時に事物において抽象的であったり、人類にとって抽象的であるでしょう。むしろそうしたことの方が多いかもしれません。そして、このような地平においては、ある写真を撮影する場合に、私たちは物を見ないと撮影できないということも、二つの意味に分解して考えてゆかなければならないと思うのです。これは私にとっても最先端の問題なので、正直しっかりとした文章が書けるとは思っていません。しかし、少し挑戦してみようと思います。
私たちは物を見るという時にも色々なレベルや種類の意識をもつと思います。例えばそれこそ『写真で伝えたい私の世界』というようなレベルで物を見て、それを撮影するということもできるでしょう。しかし一方でスキャナーで文章や画像をスキャンする時などは、実際のところ目印や指標と枠を合わせたりということを指先の感覚をもちろん使ってするのですが、その時にも、確実に視覚的に物を見て、肉体にフィードバックするようなことがあると思います。しかし、この時の物を見るということは『写真で伝えたい私の世界』というようなレベルの『見る』とは全く異なるように思うのです。このように『見る』ということにはいろいろなレベルがあって、私が『視覚以前』の写真を撮影する時に周囲の状況を確認してカメラの位置やシャッターを押す瞬間を決める時の視覚はスキャナーで文章や画像をスキャンする時の『見る』行為に近いような気がするのです。もちろんこの例えは少し不完全であって、誤解を招くかもしれませんが、いずれにしても私はその時、私が見たり感じたりしている視覚的世界のコピーを作ろうと思って写真的行為を行っているわけではなく、こうしたことは理論的に可能なことなのだということを、実例を伴ってお伝えしたいということで、この例えを用いた次第であります。もちろん私の作品を見ていただければ、それはある程度は『視覚以前』のものだとは思いますが、ただそういうものを見ていただくこととは別の角度から、そうした試みが可能であるということをお伝えし、あるいは、そうした試みの楽しさのようなものを皆様と共有したいという気持ちを持っています。
このようなことが私の考えていることであって、要約をすれば、被写体や世界というものや写真家の視覚というものから自由でのびのびと写真がそのメディウムの本性を表現できるような状態で写真を制作したいということになります。またそうした前提のうちで、画像の可能性というものを汲み尽くすことを行いたいわけです。つまり、私たちの従来的な意味における視覚的世界ではなく、画像というものの世界の広大な広がりのなかで思考して写真行為を行ってゆくことが、私の課題であるのです。(2023年7月7日)
写真についての覚書
最近——というよりずっと前から、様々な意味の『不完全さ』をどう扱うかということが、写真において全てなような気がしています。昔からあったこの感覚は、写真をとればとるほど強まってきて、揺らぐことなく、今でも写真に対する、おそらく最も率直な感覚として私の中にあるものです。写真はそれ自体の不完全さもさることながら、その外にある世界の不完全についても作用するもので、これは例えば、記録=表現という極と関係しながら、完全=不完全という極をなすものであるとも言えると思います。
写真的な実践やそれらをみるときに、様々な極が重要になってきたのだと思います。それらの中には絵画や彫刻などと共通のものもあり、また写真に特有のものもあると思います。例えば被写体=写真家、世界=写真、表現=記録、抽象=具象、美=醜などなど。ただそのなかでもとりわけ鮮明=不鮮明という、私の前述の不完全さに関する直感とも関連するような極は、写真において、重要なものだと思います。
写真の鮮明さを乗り越えるということが写真史においてとても重要な意味を持っていることは周知の事実かもしれません。その上で、私が面白いと思うのは、写真的な実践は時代を超えて、この鮮明=不鮮明という極を行ったり来たりしているように見えるということです。ピクトリアリズムに対するストレートな写真、そして報道、またそれに対するスナップの美学や私写真の(反)美学的な態度——また、いまだ歴史化されていないような私も含めた写真家によるまさに今、現代の作家の作り出している画像はそれらとも違う方法で、この鮮明=不鮮明という極の中で行ったり来たりしているように見えるのです。
写真の鮮明さを乗り越えるために撮りうる方法はスティーグリッツが指摘するように様々であって、またスティーグリッツがそうしたように、レンズやフィルムではなく被写体の性質に写真の鮮明さのハックを求めるのも、数多のありうる方法のうちの一つでしかありません。私がエドワード・ウェストンを尊敬するのは彼はその鮮明さを乗り越えるときに、被写体の性質にもカメラの側にも不鮮明を求めなかったということです。このようなことは、私の知る限りウェストンにおいて非常に早い段階で、高いレベルで実現されたものです。こうしたことは最近展示で知った近藤梓さんや京都で活動されているジョン・アイナーセンさん、奥山由之さんやパトリック・ミランさん、そして伴貞良さんといった方々にも感じることができるものだと思います。
私の写真がここまでにあげたいずれの方のものにも及ぶものだと毛頭考えておりませんが、私は私が美しいと思う写真の状態をこれからも考えてゆくことができれば、とても幸せなことだと感じています。何に対しても不鮮明ではないのに、しかし鮮明さからかろやかに抜け出しているような、そんな写真を私はみてみたいと、このように思います。(2023年8月1日)
Daishin Sakuma: farewell, 2023-